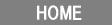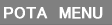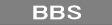|
||||||||||
2018年の秋は
浮ドンの地元八尾から瓢箪山稲荷神社へ〜
秋祭りのシーズン、地車と太鼓台…
アキアカネに急かされて〜
今ですよ今!
八尾市神立(玉祖神社) 17
だからいつもの神社・仏閣と路地・旧村探し〜
やはり浮ドンとは快晴〜タンデムポタ。。
相棒自転車はブロ君と片倉シルク号!
※マウスポインターを置いてください。
撮影:平成30年10月14日
UP日:平成31年03月20日
 ティピー(Tipi またはTeepee )とは、アメリカインディアンのうち、 おもに平原の部族が利用する移動用住居の一種である。 ティピ、ティーピーと表記されることもある。 ティーピーはスー族を始め、カナダ南部、北米平原部、北西部の、移動しながら 狩りを行う文化を持つ部族の野営用の住居である。 小さいものでは1〜2人、大きいものでは数世帯が居住できる巨大なものもある。 たいていの場合、入り口は太陽の昇る東向きに建てられる。 (Wikipediaより) ※ロケーションは最高! 八尾の町が一望〜 |
 大阪市内だって〜 ※さて、生駒山の中腹を北向いて〜 |
 大阪平野から六甲山まで一望〜 ※ |
 八尾のツインマンション ※阿倍野ハルカスも〜 |
 梅田ビル群〜六甲山 ※花園ラグビー場から 北摂の山々も〜 |
 この標高を平行移動〜 ※鏡遊び〜 ハイポーズ! |
 大坂夏の陣では 東軍が陣を張り平野を見下ろした。 丸見えですね。 ※ |
 先へ〜 ※神立ての旧村も見えます。 |
 大きな楠が目を惹きます。 鳥居正面から〜 |
 扁額 ※常世の長鳴き鳥 |
 玉祖神社(たまおやじんじゃ)は、大阪府八尾市神立にある神社。 八尾市東部・高安地区(恩智地区を除く旧高安郡13ヶ村)の氏神である。 高安大明神ともいう。式内社で、旧社格は郷社。 社伝によると創始は710年(和銅3年)に周防国の玉祖神社から分霊を勧請したもので、 その際、住吉津から上陸し、恩智神社に泊まった後、現在地に祀られたとされている。 この地に玉造部の人々が住んでいたため、その祖神を祀ったものと考えられる。 現在の社殿は、1725年(享保10年)の再建とされている。 (Wikipediaより) ※手水舎 |
 大阪府天然記念物 ※雄ですかね? |
 見返って〜 ※ |
 南向いた拝殿舎 ※ |
 拝殿舎向こうに〜 ※玉祖〜玉造に十三街道が続いている。 |
 狛犬 阿 ※吽 |
 尻尾 ※本殿舎 豊臣秀頼が荒廃した神社を再建し 大坂夏の陣で撤去され、 江戸中期の再興とか。 |
 江戸期の色彩が残されています〜 |
 本殿舎裏側〜 ※波も〜 |
 西側は残念ですね。 ※献灯も〜 |
 本殿舎前の狛犬 文化9年銘 ※拝殿舎前 狛犬 |
 室外の 絵馬は残念な状態。。 ※大きな楠の枝 |
 弁天様 ※肝試しに使われるほど怖い 像が有るんでしょうね。 |
 宇賀神(うがじん、うかのかみ)は、日本で中世以降信仰された神である。 神名の「宇賀」は、日本神話に登場する宇迦之御魂神(うかのみたま)に 由来するものと一般的には考えられている (仏教語で「財施」を意味する「宇迦耶(うがや)」に由来するという説もある)。 その姿は、人頭蛇身で蜷局(とぐろ)を巻く形で表され、 頭部も老翁や女性であったりと諸説あり一様ではない。 元々は宇迦之御魂神などと同様に、穀霊神・福徳神として 民間で信仰されていた神ではないかと推測されているが、 両者には名前以外の共通性は乏しく、その出自は不明である。 また、蛇神・龍神の化身とされることもあった。 この蛇神は比叡山・延暦寺(天台宗)の教学に取り入れられ、 仏教の神(天)である弁才天と習合あるいは合体したとされ、 この合一神は、宇賀弁才天とも呼ばれる。 (Wikipediaより) まださん探してましたね、。 ※菅原神社・稲荷社 合併末社となる。 |
 此処にも末社 ※石の祠 |
 小さな行場が〜 |
 山口神社 ※境内奥の状況 |
 蛭子神社・吉野権現・住吉神社・恩智神社・八王子神社 四柱が合祀され〜 ※ |
 日露戦役記念碑 ※玉輝碑 何やろか? |
 狛犬ではなく 鶏 ※ |
 周防国の玉祖神社には 天然記念物に指定されている黒柏鶏「くろかしわちょう」発祥の地とも言われ、 境内には顕彰碑が建つ。 また、境内で数匹が飼育されている。 (Wikipediaより) ※ |
 石燈籠 |
 鳴声は聞こえませんでしたが〜 ※ |