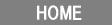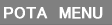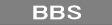物資の集積地だった市場方面に向かいます。
※賑やかだった往時を想いながら〜
|

古墳に祭られた
小さな祠
※うーんと唸りながら〜
|

境外摂社の水分神社
水を統る神
※大神宮講中銘
石燈籠
|

廣瀬神社の社森と
※太鼓橋が〜
|

市場に戻ります。
※夕日が木目を照らして〜
|

石垣、築地も〜
※
|

重厚な家屋
※
|

旧村メインの道です
※土蔵の角に〜
|

何々と〜
※川合村道路元標
|

遅めの梅の花が満開
※新旧入り交じってますが
往時が思い起こせます。
|

百貨店ですと。
※大和格子も〜
|

現代に帰ってきました。
高架道は西名阪道
※村外れの地蔵堂
庚申塚
|

【川合浜】
奈良盆地を流れる諸河川がこの付近一帯で合流して大和川となり広大な河原
を形成していることが地名の由来です。
川合は大和と河内を結ぶ大動脈 である大和川水運の発達によって古くから
栄えた集落で、江戸時代には魚梁船 (やなぶね) を使った舟運による荷揚げ
場や舟問屋もここに あり「川合浜」とも呼ばれていたのです。
古くから稲作を中心とした耕作地域ですが、大和川に接する川合には「市場」
という地名も残ります。市場という地名が残る場所は、大和川に掛かる御幸橋
(みゆきばし)の南詰め東側にあり、今も古い町並みが少しですが残されています。
現在の御幸大橋(みゆきおおはし)が掛けられる以前は、対岸の笠目(安堵町)
との往来の為に御幸瀬 ノ渡(ごこがせのわたし)があって明治の初めまで続い
ていました。
※バックの絵は…
|

サイクリングロードが有りますが〜
※この辺りが川合浜
上流方向〜
|

御幸橋も〜
※下流方向
|

右岸側に渡って〜
前の館は岡崎川水門 |