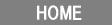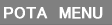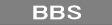|
||||||||||
春の大和路〜浮ドンと!
田原本から法隆寺へ〜
久々のタンデムぽた、いつもの旧村・神社廻り。。
超有名人・神宮寺・狛犬〜色んな出会いが!
川西町唐院(比売久波神社) 22
昨年からの目標はフルサイズ!
フルメンバーは、中々時間が取れなくて・・・
青空の下、生駒颪の北風ピープー…久々の浮ドンと〜
だからいつもの路地探し。。。
相棒自転車は片倉シルク号(昭和41年10月製)
えっ、ウルトラQ・ウルトラマンやビートルズ来日、
トヨタカローラ・グリコポッキー発売
ウォルト・ディズニー死去の年代
(Wikipediaより)
※マウスポインターを置いてください。
撮影:平成28年03月21日
UP日:平成28年03月28日
 昔と今の間が見えそう〜 ※未舗装は好きなんですが〜 |
 野良道 ※見えてるのに 何処行くネン状態。。 |
 此処を曲がると〜 ※ほら!先で迷宮から出られる〜 |
 甘かった… 道路工事中でした。 ※田の畦をトボトボと… |
 コレも又、エエ思い出〜 この近くにも小さな古墳が点在し〜 ※やっとこ今へ出ました〜 |
 向こうの丘が 寺の前古墳 ※唐院集落へ〜 |
 路地が呼んでます。 ※ |
 旧村メイン通り〜 ※ |
 脇目キョロキョロ〜 ※まって〜な! |
 大きな蔵も〜 ※脇道キョロキョロ〜 |
 大きめな村中〜 ※脇道キョロキョロ |
 先行くと〜 ※北向いた参道で〜 式内 比売久波神社サン |
 森村吉治郎顕彰碑 地元の功労者! 大正4年(1915)3月 大字唐院・保田、耕地整理にともなう揚水ポンプ設置、 水路管理等について契約を取り交わす 大正4年3月8日 (差出人)磯城郡川西村大字唐院 地主惣代 森村吉治郎 他 (奈良県立図書情報館より) ※明治四一年 従軍者(日露戦争時ですね) |
 御城主御武運長久 常夜燈 ※ |
 一の鳥居 扁額 |
 脇には島の山古墳 水辺の風景〜 ※あの部分が地続き。。。 |
 見返って〜 住宅地との間に側溝水路 ※家内安全 富社氏子 |
 先ほどの側溝水路は 土管で道路渡っています。 ※杉並木の参道〜 |
 200m位の参道〜 ※二の鳥居 |
 (浮ドン撮影) ※ |
 比売久波神社 祭神は久波御魂神と天八千千(アマハチチ)姫で 御神体は地元では桑の葉と伝えられる。 隣接する結崎の糸井神社とともに、 養蚕・絹織物の産地だったと思われる。 前には〜 |
 境内には子供の声が〜 ※大きな楠も〜 |
 拝殿舎 ※ |
 踏み石が〜古墳石室の天井石三個 島の山古墳より持ちだされた竜山石 (兵庫県高砂辺りで産出する凝灰石) ※多くの奉納石燈籠 |
 春日造本殿舎 東側 ※島の山古墳 北より |
 島の山古墳 後円部 ※前方部 |
 春日造本殿舎 裏側から〜 ※ |
 春日造本殿舎 西側 ※ |
 社殿内狛犬も〜 |
 ええなぁ〜と… ※境内風景〜 脇の寺院跡より |
 神宮寺跡(箕輪寺跡) 境内で遊ばれていた子供達の祖母さんが 「私達の子供の頃に、御堂が倒れたとか…」 ※梵字入りの水鉢 唐院氏敬白 |
 箕輪寺跡 ※ |
 明治七年〜明治十七年まで 唐院小学校の校舎として使われた。 ※箕輪焼の伝説 「唐院音頭」の十一番に以下の歌詞が有る。 『とんと唐院、よいところ 素焼きかまどに火が燃える。 加藤藤四郎、今何処 やれこい どっこい 箕輪陶器の創めどころ』 加藤藤四郎(景正)は瀬戸焼の開祖として知られている伝説的人物です。 瀬戸市には、藤四郎の陶碑が有り、其の中に、 大和国道陰村の出という記述があります。 磯城郡誌によれば唐院は道陰が転化したものとし、 大和国道陰村は、川西町唐院の可能性が高い。 箕輪焼きは現存するのでしょうか? ググッたら〜 長野県上伊那郡 箕輪焼き… |
 多宝塔型と地蔵尊 ※境内へ〜 |
 この石は礎石? ※南向いた遥拝所 三輪山? |
 明治三十六年銘 |
 拝殿社正面 ※内部絵馬を見忘れた〜汗 |
 神社境内から参道望む ※水辺の風景〜 |
 来た時と違う 旧村中の道を〜 ※淨徳寺さん |
 見返りながら〜 ※路地を彷徨って〜 |
 西へ〜 ※空き地も目立ちます… |
 西日が〜 ※煙抜きも〜 |
 唐院の村外れ〜 ※唐院交差点 飛鳥川渡ります。 |